ポン・ヌフに学ぶ在り方──“新しい”って、なんやろな?

パリに「ポン・ヌフ(新しい橋)」っていう橋がある。

名前は“新しい橋”やけど、完成したのは1607年。
実はパリで一番古い橋らしい。どこが新しいねん。
そんなツッコミを心に抱えつつ調べてみたら、意外なことに気づいた。
人は「名前と中身がズレてても、ずっとそれを使い続ける」ことがある。しかも、そういうズレた名前ほど、なぜか愛されてたりする。
ポン・ヌフ。世界一有名な「詐称っぽい名前の橋」から、なんか元気をもらった話を聞いてほしい。
“新しい橋”の正体
ポン・ヌフが「新しい」と言われたのは、名前の通り当時としては最先端の設計だったかららしい。
たとえば、
橋の上に建物を建てないという発想。
舗装された歩道があるという発想。
しっかりした橋脚で、長く使えるようにしたという発想。
今では当たり前に思えることでも、当時の橋にとってはめちゃくちゃ革命的だった。つまり、「今までの橋と違うことをした」=“新しい橋”やったわけやな。納得した。
ただ、問題はここからや。400年たって、他の橋も全部それをマネしたのに、ポン・ヌフだけが今も“新しい”って名乗ってる。いや、それ古いやろ。ええんか、それで。
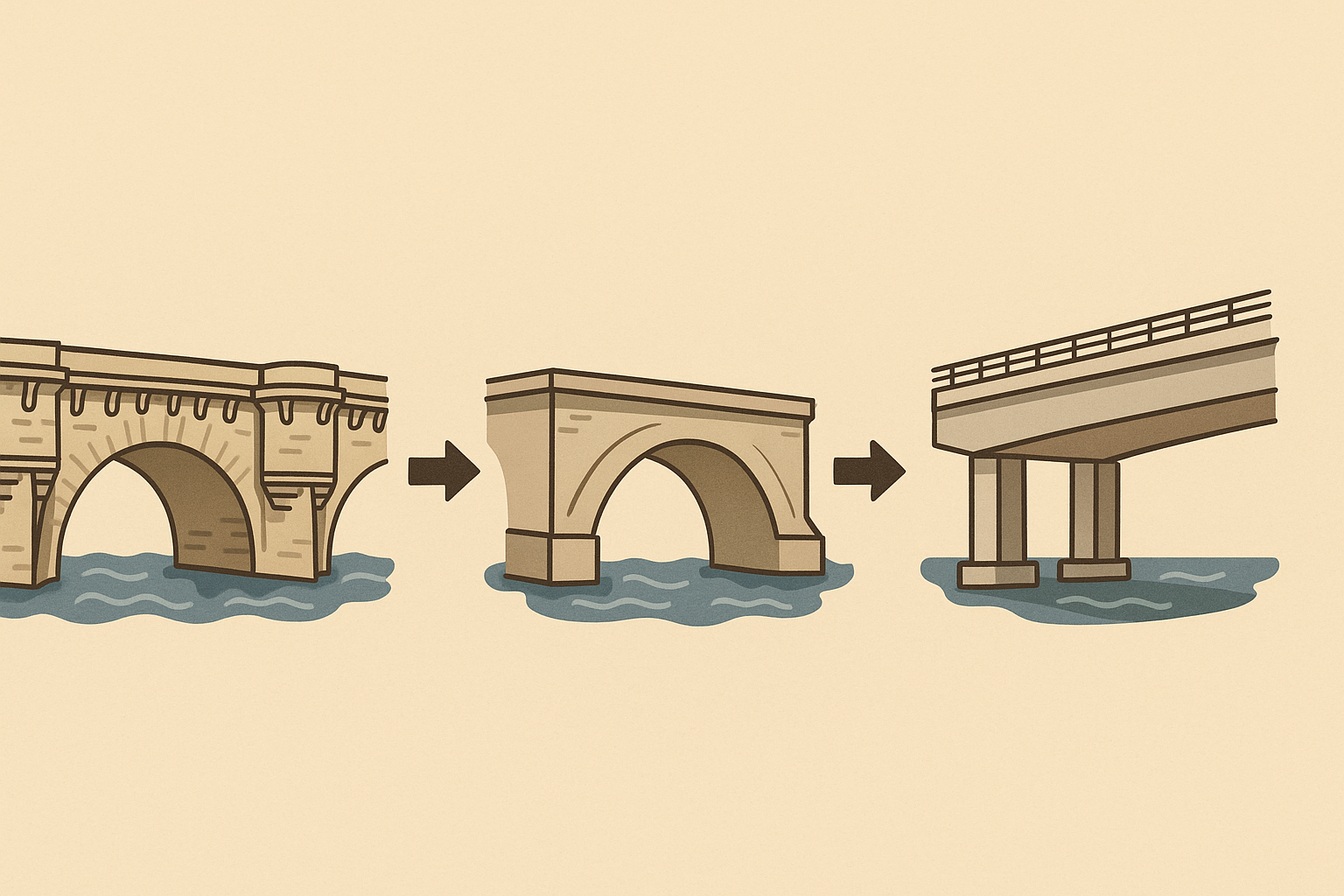
「新しい」はいつまで“新しい”なのか?
「新発売」のラベルが3年くらい同じ商品についてること、あるよな?
「新宿」は全然新しくないし、「新成人」は2日で酔っ払って「ただの大人」になってる。新人は3ヶ月で「もう慣れた?」って聞かれるし。
“新しい”って、めちゃくちゃ短命な肩書きやと思う。
でも、ポン・ヌフはそんな“賞味期限”なんて気にせず、今も堂々と「新しい橋」として立ってる。むしろ、それを愛称として世界中の人に親しまれている。
この「ズレたまま受け入れられてる感じ」、なんか不思議やけど、ちょっとかっこよくない?
他人からどう見られるかより、自分がどう名乗るか。もしかしたら、そこに“新しさ”のヒントがあるのかもしれん。
よく考えたら、「新しい〇〇」って、だいたいずっと“新しい”まま売られてたりする。
うちの近所の「新鮮市場」は創業40年やし、「新商品」の棚に並んでるやつ、半年前からそこにある。新メニューって書かれたパスタ、週4で見てるわ。
結局、「新しい」って言葉は、“その瞬間”の真実じゃなくて、“なにかを始めようとする気持ち”を表してるのかもしれん。
つまり、新しさって「状態」やなくて「姿勢」。
変わりたいとか、進化したいとか、まだまだやれるって気持ちそのもの。
ポン・ヌフが“新しい橋”であり続けてるのも、もしかしたらそういう精神の話なんちゃうか。
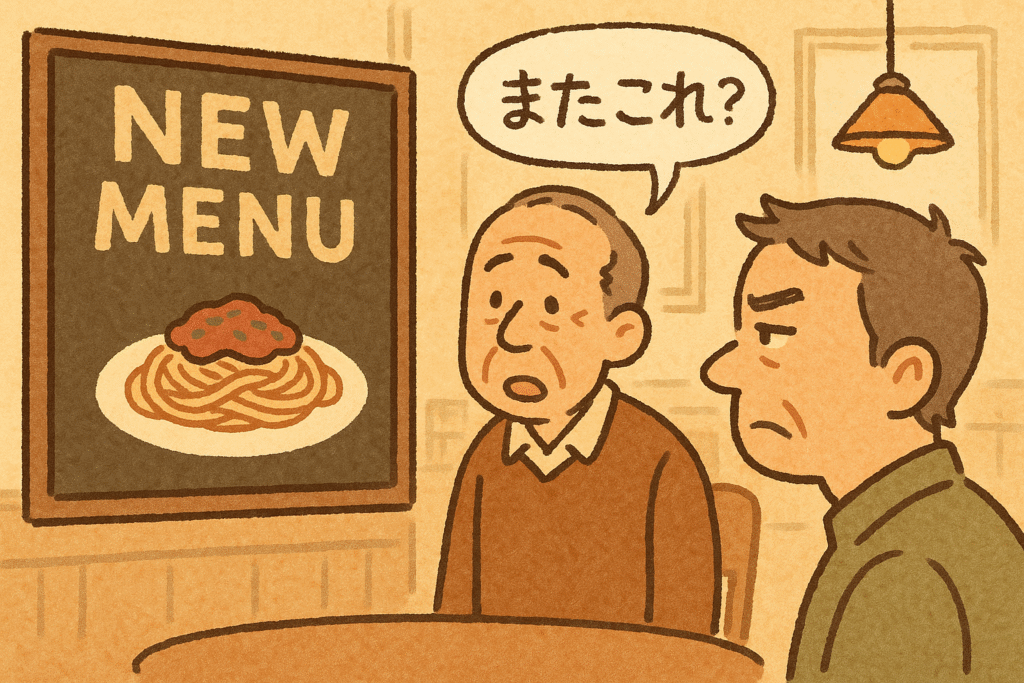
ポン・ヌフに学ぶ、“新しいままでいる”という在り方
気がつけば、俺も「新人」って呼ばれなくなって久しい。 何をやっても「もう慣れてるでしょ?」って言われるし、「新しいこと始めました!」って言うと「また?」って返される。
でも、ポン・ヌフを見て思った。400年も経ってるのに、あの橋はいまだに“新しい”と名乗っている。
誰ももうツッコまない。「古いやん」とか言わない。
ただ、「新しい橋」として、堂々とそこにある。
新しさって、他人が決めるものやなくて、自分が持ち続ける姿勢なんちゃうかな。世間にどう言われようが、自分の中で「これは新しい挑戦や」と思えてるなら、それでええんちゃうか。
ポン・ヌフのように、外見は変わっても、内側で“更新し続ける”気持ちを持っていたい。
さいごに
今日もパリでは、最古の橋が「新しい橋」として立っている。
新生児も、新成人も、新人も── いつのまにか“新”が取れて、 ただの子ども、ただの大人、ただの社員になる。
でも、ポン・ヌフを見て思ったんよ。
新しいって、名乗り続けることやなくて、姿勢の話なんちゃうかって。
慣れても、古くなっても、 心のどこかに「今がはじまり」って思える自分でいたいな、って。
